24歳会社員のおにぎりです。
私は、生物系の大学出身です。
この記事では、生物専攻の学生にぜひ読んでほしい一冊として、
泉貴人さん著『水族館のひみつ』をご紹介します。
本書は、進路を考えるうえでヒントになる本です!
生物を専攻している学生のみなさん、こんな経験はありませんか?
- 授業で学ぶ知識は面白いけれど、実際にどんな現場で活かせるのかわからない
- 研究を深めたいけれど、将来どんな仕事につながるのか想像がつかない
そんな方にこそおすすめしたいのが、泉貴人さん著『水族館のひみつ』です。
この本を手にすると、
- 学んできた分類学や生態学の知識が社会にどう役立つかがわかる
- 水族館というフィールドで働くイメージが鮮明になる
- 生物研究を社会や教育に還元する道を考えるきっかけになる
といった未来が手に入ります。
「水族館が好きだから」だけでなく、
「学問として生物に向き合っている学生」に強く響く一冊です。
『水族館のひみつ』はこんな学生におすすめ!
- 生物を専攻している高校生・大学生
- 将来、水族館や動物園で働きたいと考えている人
- クラゲやイソギンチャクの生態に興味がある人
この本を読めば、生物系の研究の延長線上に「水族館で働く」という
新しい進路の選択肢を見つけることができます。
水族館から考える社会問題|イルカ飼育の是非
本書は、水族館の楽しさだけでなく「社会問題」にも触れています。
特にイルカの飼育やショーは国際的に議論の的になっており、
水族館の存在意義そのものが問われるテーマです。
生物系の研究を志す学生にとって、この問題は避けて通れません。
生物を研究するとはどういうことか、社会とどんな関わりを持つべきか
――そんな問いを投げかけてくれます。
本書の内容
泉貴人さんは、海洋生物学者です。
福山大学生命工学部・海洋生物科学科で講師をされています。
本書では水族館と動物園の違いから始まり、バックヤードの仕組み、
クラゲ展示の難しさ、社会問題に至るまで幅広く解説。
読み進めるうちに「水族館=癒しの空間」という単純なイメージが覆され、
生物を扱う現場の奥深さを実感できます。
生物系を学ぶ学生にとっては、卒業後に水族館関連の仕事を目指す際に、
講義で学んだ知識が現場でどのように活かされるのかを知る貴重な機会になるはずです。
本書で学んだこと
水族館と動物園の違い(生物の入手ルートに注目)
動物園では「ワシントン条約」によって展示できる生物の種類が厳しく制限されており、
希少種を集めること自体が難しいため、展示の多様性も限られてしまいます。
一方、水族館では条約の対象外となる魚類や無脊椎動物が多く、入手ルートも豊富です。
漁師との協力や採集活動を通じて、多種多様な生物を集めることができます。
生物学を学んでいると「分類」や「保護」といった視点を知識として理解できますが、
この本を読むことで、それらが実際の現場でどのように実践されているのかを
具体的に知ることができます。
バックヤードの秘密(予備水槽は生命線)
展示水槽の裏にある「予備水槽」の存在は、水族館運営の要です。
- 病気や繁殖期で弱った個体を保護する
- 展示水槽が空にならないよう常に待機させる
- 環境を調整して個体をベストな状態で見せる
こうした役割を果たす予備水槽があるからこそ、華やかな展示が成り立っています。
これは単なる飼育管理ではなく、実験室でのコントロールや研究に近いもの。
生物を「展示対象」として扱う難しさを学ぶことができます。
クラゲ展示の舞台裏(水槽の種類と繁殖)
本書で特に印象的だったのが、クラゲの飼育方法についての解説です。
クラゲは流れがないと沈んで死んでしまうため、
「クライゼル(太鼓型)水槽」が欠かせません。
水族館でよく見かけるこの形の水槽には、
実はきちんとした理由があったのだと気づかされました。
さらに、クラゲの繁殖についてはイラスト付きでわかりやすく説明されており、
学びが多かったです。著者の研究対象がクラゲやイソギンチャクということもあり、
それらの生態に関する記述が豊富で、普段触れることのない知識の世界に出会うことができ、
とても興味深く感じました。
個性豊かな水族館紹介(室蘭水族館のユニークな工夫)
全国の水族館が多数紹介されているのも本書の魅力です。
なかでも北海道・市立室蘭水族館では、生物の解説に「美味しさの星評価」
が付けられており、そのユニークさに驚かされました。
正直、「水族館の生き物を美味しそうだなんて思ってはいけない」と思っていたので、
この取り組みは衝撃的でした。
しかしよく考えてみると、これは「人間と生物との関係性」を
ユーモラスに伝える工夫でもあります。
食材としての視点を加えることで、生態系と私たちの生活とのつながりを考えさせられるのです。
生物系を学ぶ学生にとっては、学んでいる知識を「社会にどう伝えるか」を
考える上での参考になるのではないでしょうか。
まとめ|学んだ知識を“生きたもの”に変える一冊
泉貴人さんの『水族館のひみつ』は、
授業や研究室で得た知識を「現場」とつなげ、
未来の進路や研究テーマを考えるきっかけになる一冊です。
次に水族館を訪れるとき、きっと展示を眺めるだけでなく
「裏側にある努力や技術」にも思いを馳せるようになるでしょう。
水族館の見方を180度変え、生物学をもっと面白くしてくれる本。
生物系の学生なら、ぜひ手に取ってみてください!
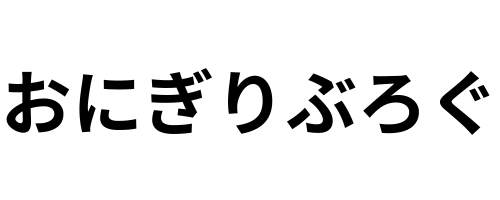
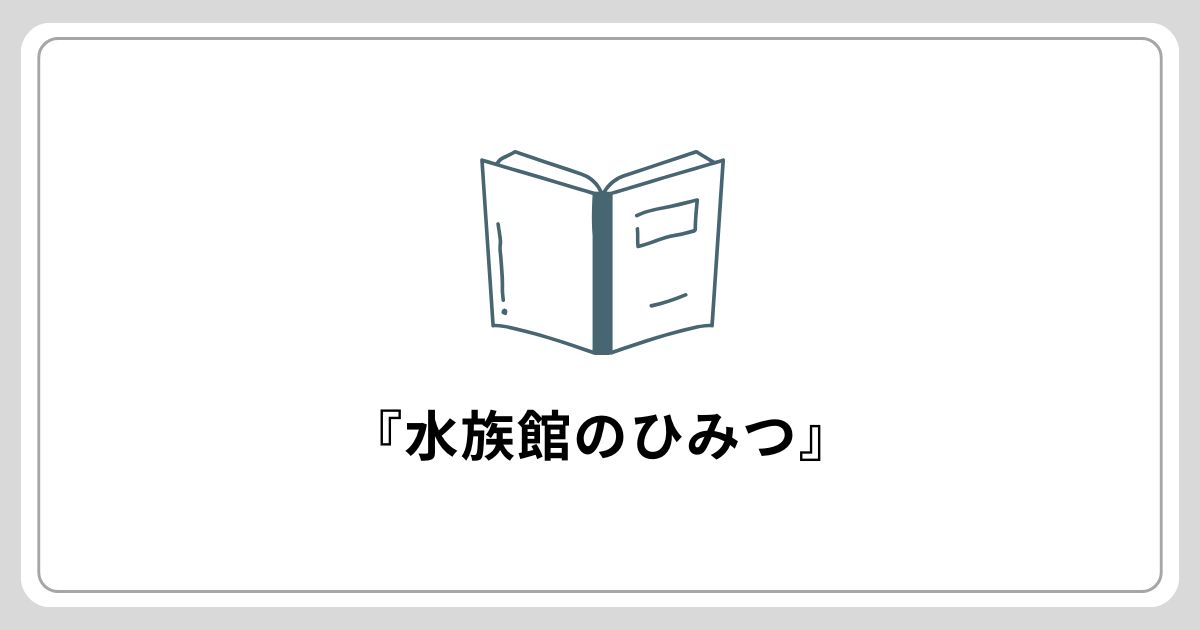



コメント